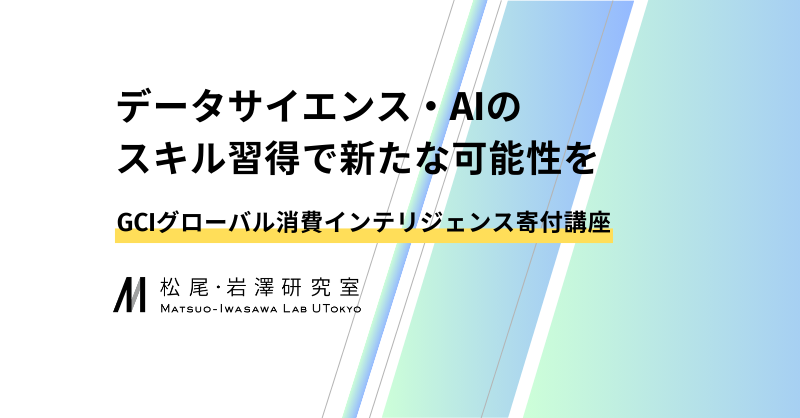
プログラム
【松尾・岩澤研究室監修】グローバル消費インテリジェンス寄付講座~GCI 2025 Winterのご案内~
解説記事

こんにちは。一橋map運営のRです!
シラバスだけでは読み解けない授業の特徴や魅力を、担当教員にインタビューしながら紹介する「超!シラバス」。
今回は「金融ファイナンスBⅠ・Ⅱ」を担当されている山田先生にインタビューしてきました!!
※本記事に掲載されている内容は、取材時点でのものです。最新情報はシラバス等をご確認ください。
科目分類:経済学部 発展科目(300番台科目)
開講時限:他
形式:オンデマンド・非抽選
担当教員:山田春菜 先生
現在は、拓殖大学政経学部経済学科で助教を務めています。一橋大学では、加納隆先生が担当されていた金融ファイナンスBⅠ・Ⅱを数年間だけ交代して担当しています。私が大学院を一橋大学で過ごしていた際は、加納先生に指導教官を務めていただいていました。
研究では「国際金融」という分野を主に扱っています。特に新興国・途上国と先進国との間に流れる資本フロー(お金の動き)について、発生する理由やきっかけ、国内経済に及ぼす影響を中心に研究しています。
BⅠ・BⅡを通じて、学部レベルの基本的な国際金融論について学習します。
BⅠでは、先ほども触れた資本フローや、為替レートが大きなトピックです。為替レートがどのように決まるのかや、どのような要因で変わるのかなどの話をする予定です。
BⅡでは歴史に関する話も多くなります。通貨体制を例に挙げると、昔は金本位制が採用されていて、金と各国の通貨がいつでも交換できる時代でした。その後、今度はドル本位制を経て、先進国では現在の変動相場制に移行しました。そうした通貨体制の歴史とそれに付随して起こった色々な出来事をカバーして、現在の国際金融の問題についても少し触れていく、というのがBⅡの流れです。
国際金融は、国と国とのやりとりを考えるので、マクロ経済寄りの知識は必要になってくるかと思います。また、例えばある国の利子率が変化した時に、どのように為替レートが変化するかを、グラフを使って議論していく場面では、少し抽象的な思考力が求められてくると思います。
この授業は英語で進めていくので、内容がわからなかった時に「日本語なら理解できるかも」と思ったら自分で日本語の教科書を読んでみる等の主体性にも期待したいです。指定のテキストは古い版ですが日本語訳も出ています。
経済学の第一言語は英語と数学といわれるほどで、英語は不可欠なものです。これから卒業論文に向けて英語論文等、経済学に関する基本的な単語を嫌というほど目にする事になると思うので、あらかじめ講義でその用語に触れられるのは大きいと感じています。私自身も大学院での講義がいきなり英語だったので、わからない単語をひたすら日本語訳していくというのがはじめのうちは大変でした(笑)。
なお本講義では、質問は日本語でも英語でも受け付けていますので、何か困ったことがあったら私の方にメールしていただけると嬉しいなと思います。
週に一回のクイズとテイクホーム型の期末試験の2つを実施する予定です。クイズは全て選択式で、わからなければ友達と相談してもらっても構いません。
期末試験については問題をオンライン上で公開して、そこから数日~一週間の期間を置いて、締め切り日までに提出していただく形です。内容は選択式だけでなく、計算問題や記述問題も含まれています。また、答案に関しては必ず英語で書いていただく形になっています。こちらも友達と相談してOKです。
開講科目が英語ということで、将来は留学に行きたいと思っている方や、卒業論文の執筆の際、英語で経済学の論文を読んでみたいという人に特におすすめです。英語で経済学を学ぶためのファーストステップとして取っていただけるといいのかな、と思います。
LINE登録はお済みですか?
一橋mapの記事をお読みいただきありがとうございました。