
プログラム
保護中: 【超!シラバス】民法(総則・物権)ってどんな授業?先生に聞いてみた!
インタビュー・レポ
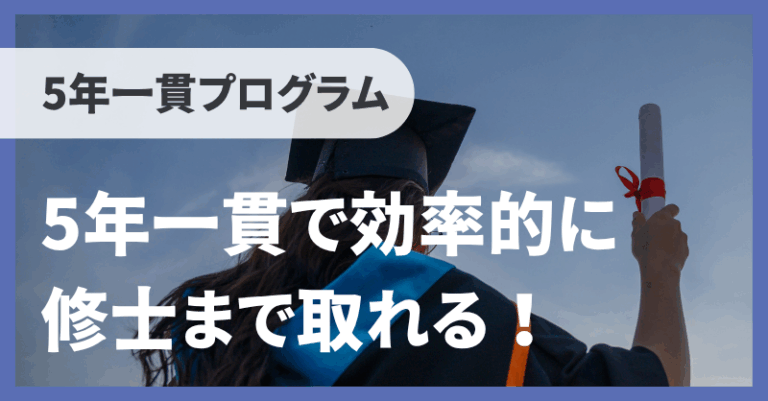
こんにちは!一橋map運営メンバーの商学部1年はちです。
一橋大学の各種プログラムを利用して、授業以外での学びを経験する先輩の体験談を紹介していく、一橋mapの「一橋プログラム体験記」シリーズ。
「これからプログラムへの挑戦を検討している」「考えていなかったけど、実際の参加者の経験談を聞いてみたい」——そんなみなさんの参考となるようなインタビューをお届けします。
一人でも多くの一橋生が新しい出会い・挑戦をする一助となれば幸いです!
今回は、「5年一貫プログラム」に参加されている先輩お二方に、対談形式でインタビューをしてきました!
修士に興味がある人だけでなく、留学や進路で迷っているという方にもおすすめです!
<先輩プロフィール>
名前:M.Nさん
学部:一橋大学 社会学部4年生(インタビュー当時)
参加したプログラム:社会学部・社会学研究科「学部・大学院修士課程5年一貫教育プログラム」名前:R.Iさん
学部:一橋大学 経済学部4年生(インタビュー当時)
参加したプログラム:経済学部・経済学研究科「学部・大学院5年一貫教育システム」
※本記事に掲載されている内容は、取材時点でのものです。制度の詳細や募集要項などの最新情報は各学部の公式サイトをご確認ください。
ーーまず初めに、どのような制度なのか簡単に教えてください!
M.Nさん:
社会学部では「学部・大学院修士課程5年一貫教育プログラム」という名称で、学部入学から最短5年で学士号と修士号を取ることができます。
R.Iさん:
経済学部では「学部・大学院5年一貫教育システム」という名称ですが、同じような仕組みです。商学部や法学部にも同様の制度がありますが、ソーシャルデータサイエンス(SDS)学部にはないそうです。
ーー学部ごとに少し違う部分があるのですね!
※プログラムの名称は学部・研究学科によって異なりますが、本記事では統一して「5年一貫プログラム」と表記します。
ーー参加までの経緯や、参加に至った理由を教えてください!
M.Nさん:
以前から、長期留学に行きたいと思っていたのですが、一橋の長期留学は3年生以降で就活の時期とかぶってしまうため、もともと5年間在学しようと思っていました。その中で5年一貫プログラムの存在を知って、同じ5年間在学するなら修士まで取れた方が、一石二鳥だと思ったことがきっかけです。
また、留学中に興味のある分野について集中的に学んだことで、学部レベルの勉強では物足りないと気づいたことも理由です。在学期間を一年間延ばして、ゼミの先生のもとでさらに専門的に学んだら面白そうだなと思いました!
R.Iさん:
元々、大学院に行きたかったため、1年生の時から大学院について少しずつ調べていく中で、5年一貫プログラムを知りました。
私は1年間浪人して大学に入学したため、その分を取り戻せると考えたことも志望理由の一つです。また、学部より高い水準で研究を深堀りしたいと思っており、5年一貫プログラムは自分に合うと感じて志望しました。
ーーよろしければ研究テーマを教えてください!
M.Nさん:
国際政治について研究しています。具体的には、太平洋戦争後の日本に侵略されたアジア諸国の対日認識がテーマです。文献調査などの定性分析のほか、データを用いた定量分析も行います。
R.Iさん:
計量経済が研究テーマで、MATLABや R、Excelなどを用いてデータ分析を行っています。私は経済学部ということもあり、株価の変動要因の推定をしたいと思っています。現在は分析のデータを収集しているところです。
ーー実際にプログラムに参加すると、どのような流れで活動していくのでしょうか?
M.Nさん:
5年一貫プログラムに参加すると、学部4年生でありつつ修士1年生という状態になるので、学部ゼミと院ゼミの両方に参加することになります。
私の場合、学部で所属しているゼミと同じ教授が開講している大学院のゼミにそのまま所属しています。学士論文を書く時期は他の人と同じですが、大学院の在籍年数が通常より一年間短い分、修士論文を書く時間が限られています。そのため、学士論文を中間発表のように位置づけ、大学院でも同じ研究テーマを継続して修士論文を書く人がほとんどです。
R.Iさん:
私の場合もほぼ同様で、学部4年生時に、大学院のゼミにも参加し、そこで修士1年で学ぶ基礎的な内容を勉強をしました。学士論文を書いた一年後には修士論文を書かなければいけないため、教授から論文の内容を繋げるように言われました。
ーー学部のゼミと大学院のゼミではどのような違いがありますか?
M.Nさん:
大きな違いは外国人の留学生の割合です。学部では30人のうち2人でしたが、大学院では7人中5人が外国人でした。
R.Iさん:
留学生は確かに多く感じます。特に東南アジアからの人が多い印象です。
また、同じ先生から学んでも、大学院のゼミでは内容的にレベルが上がり、踏み込んだ分野を勉強することが多いです。
さらに、大学院では修士論文に向けて、多い時には毎週研究発表を行うことになります。この研究発表のために参考文献を読んだり資料をまとめたりする必要があり、5年生の間は学部生の活動とも重なるので忙しく感じると思います。
M.Nさん:
忙しさでいえば、5年一貫プログラムと留学を両立する場合も忙しくなりやすいです。そのためプログラムに参加する前は不安だったのですが、同じゼミに両立していた先輩がいたので、その方に実際にお話を伺いイメージが湧いたので、挑戦することに決めました。
ーープログラムの選考の流れと、大変だったことがあれば教えてください!
R.Iさん:
経済学部で特に大変だったのは単位の取得です。学部3年生の夏までに経済学部の科目が50単位以上必要になるんです。また、学部3年生の10月頃までに研究計画書を書いて教授に確認してもらい、年明けにある面接で合格する必要があることも大変でした。
〇経済学部5年一貫システムの選考の流れ
選考時期:11月頃~
満たすべき成績要件:
・経済学部教育科目について3 年次の夏学期までに50 単位以上取得
・100 番台、200 番台コア科目に関する卒業要件を満たし、これらの成績が GPA 3.0 以上
必須試験:
・口述試験
提出書類:
・志願票
・3年次夏学期までの成績証明書
・推薦書(ゼミナール担当教員等に経済学部・経済学研究科事務室へ直接提出するよう依頼しておく)
M.Nさん:
社会学部では、選考時期が12月〜1月で経済学部より少し遅く、1月中に口述試験と選抜結果発表があり、5年一貫プログラムの内定が決まりました。経済学部と異なり、単位数の決まりはないため、そこまで厳しいとは感じませんでした!
また、プログラム履修中の4年次に大学院入試を受験し、合格する必要があります。
GPAが3.0以上の場合は、特別選抜という形態の院試に出願できるのですが、これは7〜8月に出願をして、9月に合格発表があります。特別選抜の場合は、研究計画書などの書類と面接のみで受験でき、筆記試験はありません!
〇社会学部5年一貫プログラムの選考の流れ
選考時期:11月頃~
満たすべき成績要件:以下の要件のいずれか
・社会学部グローバル・リーダーズ・プログラム(GLP)履修
・2024 年度春夏学期までの GPA が 3.0 以上
必須試験:
・口述試験
提出書類:
・志願書
・研究計画書
・成績証明書(2025 年春夏学期までのもの)
・指導教員等の推薦書(ただし、GLP 担当教員・導入ゼミ担当教員・入門ゼミ担当教など、出願者の学修能力・ 関心について十分に評価できる本学教員をもって代えることも可能 )
・志願書の「特記できる資格・スコア、経験など」に記入した場合、関連する証 明書等のコピー(証明書類がない場合は不要)
※各学部の選考の詳細や最新情報は記事冒頭のリンク先から募集要項をご覧ください。
ーー5年一貫プログラムに参加して良かったことはありますか?
M.Nさん:
私の場合は、元々5年間在籍する予定で考えていたため、時間を有効活用できることが一番のメリットでした!
R.Iさん:
留学で留年する人も多い中で、M.Nさんは「時間を無駄にしたくない」という考えを持って5年一貫プログラムに参加していて、とてもストイックだなと思います。
留学に行く人だけではなく、大学院に興味があるという人にとっても、5年一貫プログラムに参加すると、在籍年数が短くなり、学費を抑えることができます。学部3年生時点で単位を取り終わる人も多いと思うので、学部4年生の空いた時間を短縮できるというのはかなり魅力的ではないでしょうか。
ーープログラムに参加する際に注意した方がいいことはありますか?
R.Iさん:
参加を悩んでいる人は、自分の進路の幅を広げるという意味で、とりあえず申し込んでおくことも選択肢になると思います。
M.Nさん:
確かに、社会学部の応募要項でも辞退が可能だと明言されていたので、まだ確定していなくても応募するという選択もありだと思います。
R.Iさん:
また、ゼミ選びの場面では、5年一貫プログラムの学生を受け入れたことがあるなど、プログラムに対して理解のある教授のゼミを選ぶとスムーズです!
M.Nさん:
私も、ゼミ選びは重要だと思います。5年一貫プログラムの制度自体をあまり良く思ってない教授もいますが、出願のためには教授の署名が必要なので、教授の理解は大切です。早いうちからこのプログラムを志望するならば、学部のゼミ選びから考慮してもいいと思います。
ーー最後に、5年一貫プログラムへの参加を考えている方にメッセージをお願いします!
M.Nさん:
留学に行って延びた一年を使い、専門的な内容を学びながら修士まで取れる良い制度だと実感しています。社会学部の選考はそれほど大変ではありませんが、もし留学との両立を考えているなら、学部3年生の春夏のうちに発展科目を取っておいたり、フル単しておいたりすると楽になると思います!
R.Iさん:
「文系は大学院に行くとキャリアに不利」と言われることもありましたが、今は時代が変わってきていて、大学院に進学しても有名企業に採用される人は多くいます。実際に就活を始めてみても、大学院に行くことは決してマイナスではないと感じているところです。皆さんもぜひ、選択肢の一つとして考えてみてはどうでしょうか?
ーーお二人とも、本日はありがとうございました!
LINE登録はお済みですか?
一橋mapの記事をお読みいただきありがとうございました。