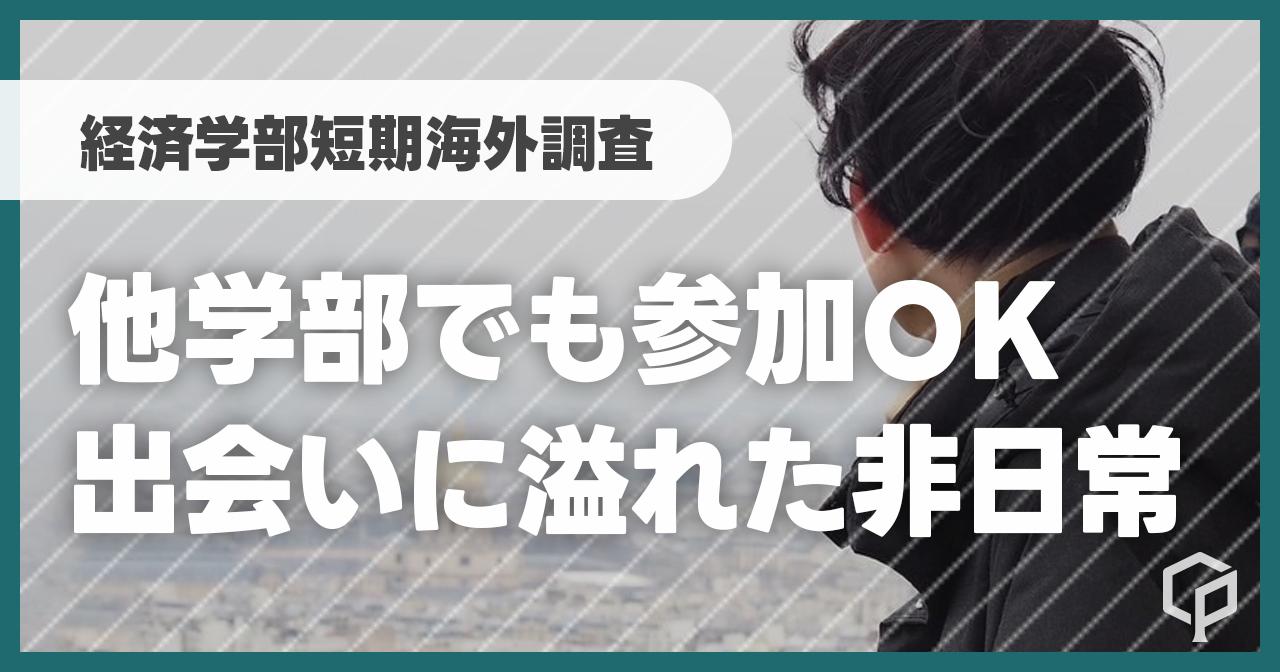
プログラム
他学部OK!人・企業・先輩…出会いに溢れた非日常/経済学部短期海外調査【一橋プログラム体験記】
インタビュー・レポ
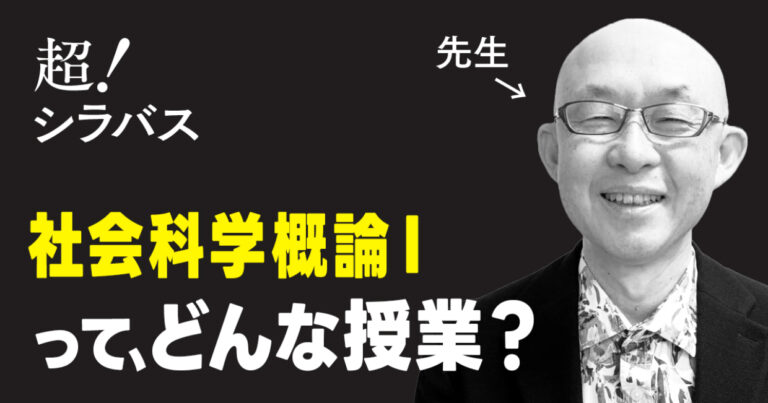
こんにちは。一橋map運営チームのNです!
シラバスだけでは読み解けない授業の特徴や魅力を、担当教員にインタビューしながら紹介する「超!シラバス」。
今回は社会学部1年生の必修授業である「社会科学概論Ⅰ」を担当される、菊谷和宏先生にお話を伺いました!
※この科目は数土先生とお二人で担当されているため、先生によって授業内容・評価方法が異なることを踏まえたうえでお読みください!
※本記事に掲載されている内容は、取材時点でのものです。最新情報はシラバス等をご確認ください。
広く言えば社会学ですが、社会学史や社会思想、社会理論といった社会学の基盤にあたる分野です。イメージとしては哲学が近いのですが、厳密には哲学でもない分野になります。
高校時代、授業の資料集で見かけた社会有機体説に興味を持ったのがきっかけで、社会について関心を持ち、大学で社会学を学びたいと思いました。当時、社会学部を名乗る大学が一橋大学のみだったので、この大学に入学し大学院まで進みました。なので、今回お話する「社会科学概論Ⅰ」を私も受講しました。
新入生向けの導入科目です。教員二人で担当しており、それぞれに定員があるため、希望を出したうえで抽選によっていずれかの授業を受けることになります。必修授業になっているため単位をとらないと卒業できない授業の一つになります。
この授業は導入授業として、高校までの学習から大学の学問へ切り替える役割を担っていると考えています。必ずしも社会学部生の全員が狭義の社会学を専攻するわけではないので、人文・社会科学への種まきになればよいなと思います。
具体的には何をどう問うべきか、つまり問いの形成に重きを置いています。「質の良い問いとは何か」を実技として習得してほしいですね。「社会科学とは何か」がこの授業の中で大きな問いとなっており、これについて新入生側が議論できる環境を作っているので、そういう意味で私はこの授業を「考えるという実技科目」だと捉えています。
自分で考えるということ、大学で学問をするとはどういうことかを経験してほしいですね。「思う」のではなく「考える」。新入生同士で刺激しあいながら、「なぜ」を問い、根拠を明確にしてしっかり考えられるようになってほしいと思います。答えを知ることではなく(そもそも答えがあるわけではないので)、適切な問いを自ら立てることのできる基盤づくりをしましょう。
今はオンデマンド開講のため、「社会科学とは何か」にまつわる期末レポートで評価しています。穴埋め形式などではなく、自分でテーマを考えて論述してもらいます。以前に対面で行われていた時は、期末レポートかテスト形式をとっており、議論の場で優れた発言をした人に加点なども行っていました。
いずれにしても暗記ではなく、基礎的な概念を理解したうえで的確な問いを立てられるかどうかが評価対象となります。
学問を楽しんでください!今まで学びを強いられてきた人が多いかもしれません。けれど本来学問は楽しいものです。この授業で学問をすることを楽しんでもらえれば導入科目としての役割は果たせると思っております。
LINE登録はお済みですか?
一橋mapの記事をお読みいただきありがとうございました。