
プログラム
オーストラリア・クイーンズランド大学/海外語学研修【プログラム体験記】
インタビュー・レポ
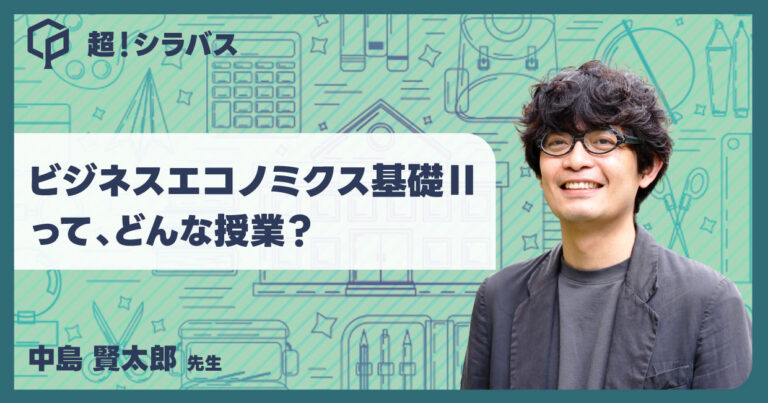
こんにちは!一橋map運営メンバーの商学部1年はちです。
シラバスだけでは読み解けない授業の特徴や魅力を、担当教員にインタビューしながら紹介する「超!シラバス」。
今回は、商学部で秋学期開講の「ビジネス・エコノミクス基礎II」の授業を担当される中島賢太郎先生にインタビューをしてきました!
※本記事に掲載されている内容は、取材時点でのものです。最新情報はシラバス等をご確認ください。
ビジネス・エコノミクス基礎II
科目分類:商学部基礎科目
開講時限:秋学期 火1・金1
担当教員:中島賢太郎先生
形式:対面、抽選なし
私は経済学者で、主に応用ミクロ実証経済学と空間経済学を扱っています。応用ミクロ実証経済学は、ミクロ経済学の理論を前提にしつつ、実際のデータを用いて仮説を検証する分野です。その中でも、特に空間にフォーカスした空間経済学のジャンルに力を入れているほか、都市やイノベーションに関する研究にも取り組んでいます。
最近では、特許情報や衛星画像、スマートフォンのGPS、あるいは昔の地図情報など、地域の経済活動や、人々の営みを詳細に把握することができるさまざまなデータを使って、なぜ地域間で経済活動の大きさに違いがあるのかとか、そもそもなぜ都市ができるのかなどについての研究を行っています。
経営学に近いテーマでは、「企業の中で何が起きているのか」について、データを使って解き明かす研究を進めています。 例えば、ある企業の従業員にセンサーをつけてもらい、誰と誰がどれくらい話したかや、会話の中でどう情報交換しているかというデータを集めて、コミュニケーションがそれぞれの従業員の生産性やパフォーマンスへの影響を調べるような研究も行っています。
商学分野に限らず、社会科学全般で使うデータ分析の方法について学べるということが、この授業を受ける大きなメリットです。昨今、企業でのデータ分析の機会が増えており、多くの卒業生がデータを扱う職種に就いていると思います。そのため、この授業で身につくデータ分析の考え方やスキルは、多くの学生にとって社会に出てからも役に立つスキルではないでしょうか。
「R」を使った実習では、社会科学特有のデータ分析方法を実際に体験します。
社会科学におけるデータ分析は、自然科学や工学の場合と異なり、条件を完全にそろえた実験ができないことが多いです。。例えば、理科の実験で「物が燃えるためには酸素が必要である」という仮説を調べるときには、酸素が入った瓶と酸素が入っていない瓶で、それ以外の条件をすべて揃えて比較することができます。一方で、社会科学の研究で、「社外取締役を入れたら会社のパフォーマンスが改善する」という仮説について検証する場合、社外取締役を入れる会社は、他の施策も積極的に進めているかもしれません。 そのため、単純な比較では社外取締役を置く効果を正確に測定できないのです。
社会科学分野では、このように複雑な要因が絡み合う状況で、因果関係を分析するための理論やテクニックが発展しています。実際に、2019年、2021年のノーベル経済学賞は、このような因果関係を統計的に分析するための手法を考案したことに対して与えられています。ビジネス・エコノミクス基礎IIの授業では、まずその理論を学び、その上で実際に自分の手を動かしてデータを分析する、という流れで学んでいきます。
この講義は、社会科学を学ぶ人を対象にしたテキストに沿って進めます。プログラミングはやれば誰でも必ずできます。講義を聴いて、テキストを読み、そして何より自分でプログラムを書くことに取り組んでもらえれば、プログラミングに関する専門的な知識がなくても全く問題ありません。
まず第1章では、「因果効果」などの社会科学におけるデータ分析の主流の考え方を学んでもらいます。「因果効果」というのは、単なる相関関係ではなく、原因と結果の関係性を明確に捉えることを目的とした概念です。「因果効果をできるだけ信頼できる形で検証する」、「統計的に因果効果を推定する」という基本的なコンセプトについて、理解してもらいたいと思っています。
第2章の「因果関係」では、この因果効果の測り方について学びます。この章では2021年のノーベル経済学賞の受賞理由の一つになった研究で用いられたデータなどを実際に分析します。第3章の「測定」では、データを測定する方法、第4章の「予測」では、社会科学にかかわらずデータ分析でよく使われる回帰分析について学びます。第5章は、シラバスでも特筆していない通り、授業では大きく取り上げません。
第6章の「確率」と第7章の「不確実性」は、難しいですが特に重要な内容である、「どのような状況であれば、因果効果があると言ってよいのか」というテーマについて議論します。
例えば、「社外取締役がいる会社」と「いない会社」ではどちらのパフォーマンスが高いか検証するために、それぞれの株価の平均値を比べるとします。その際、平均値が完全に一致することは、まず考えられず、必ずどちらかのグループの平均値が高くなるでしょう。しかし、単に平均値の差を見るだけでは、その差が誤差のようなものなのか、社外取締役を設置したことによる効果なのかの判断は難しいです。
そこで、確率の考え方を使うことで、「どの程度の差があれば、誤差ではなく社外取締役を置いたことによる株価への効果があると言えるのか」の基準を決めることができるのです。
このように、講義全体を通じて、社会科学のデータ分析の際に知っておくべきコンセプトやテクニックについて、自分で手を動かしながら学んでいきます。
確かにそうですが、授業から小テストの回答までのペースは、毎年およそ一週間と、比較的長めにとっているので、そこまできついスケジュールではないと思います。
この講義を理解する上では、深い前提知識は特に必要ありません。統計や確率に関する、高校で学んだ範囲の知識があれば十分です。そのため、知識を詰め込むよりも、この講義で学んだテクニックを使って、「今後何に生かせるか」や、「どういうデータを使ったら他の授業で学んだ理論を検証できるのか」を考えながら、問題意識を持って授業を受けてもらえると良いと思います。ただ、プログラミングは実際に自分で書かないと全く上達しないので、手を動かすことだけは意識してほしいです。
ⅠとⅡにはそれほど強い関連がないため、Ⅰを履修していなくても授業についていくことは可能です。ただし、企業の活動について経済学のツールを使って考えることや、ビジネスや企業を見る目を養うという意味では、商学部全体の学びとしてどちらも非常に重要だと思うので、両方受けておくことをおすすめします。
シラバスの通り、5回ほど行う小テストを通じて成績を評価する予定です。
小テスト(100%):教科書の章単位を目安に、全体を通じて数回行うことを予定している。また、小テストはmanabaにて行う。詳細については随時manabaにて告知する。(シラバスより)
社会科学の場合、仮説をデータで検証するために独特のテクニックを必要とするなど、特有の難しさがあります。この授業を通じて、そのような難しさを理解した上で、データ分析の方法を知っておくことは、世の中に出てくるデータ分析の結果を解釈する際にも役立つかもしれません。
ぜひ積極的に学ぶ姿勢をもって、データ分析の奥深さを実感してほしいと思います。加えて、冬学期に応用ミクロ経済分析という講義を実施します。都市や空間について経済学とデータから分析する授業で、そちらもとても面白いと思いますので、よければシラバスをぜひ見てみてください。
LINE登録はお済みですか?
一橋mapの記事をお読みいただきありがとうございました。