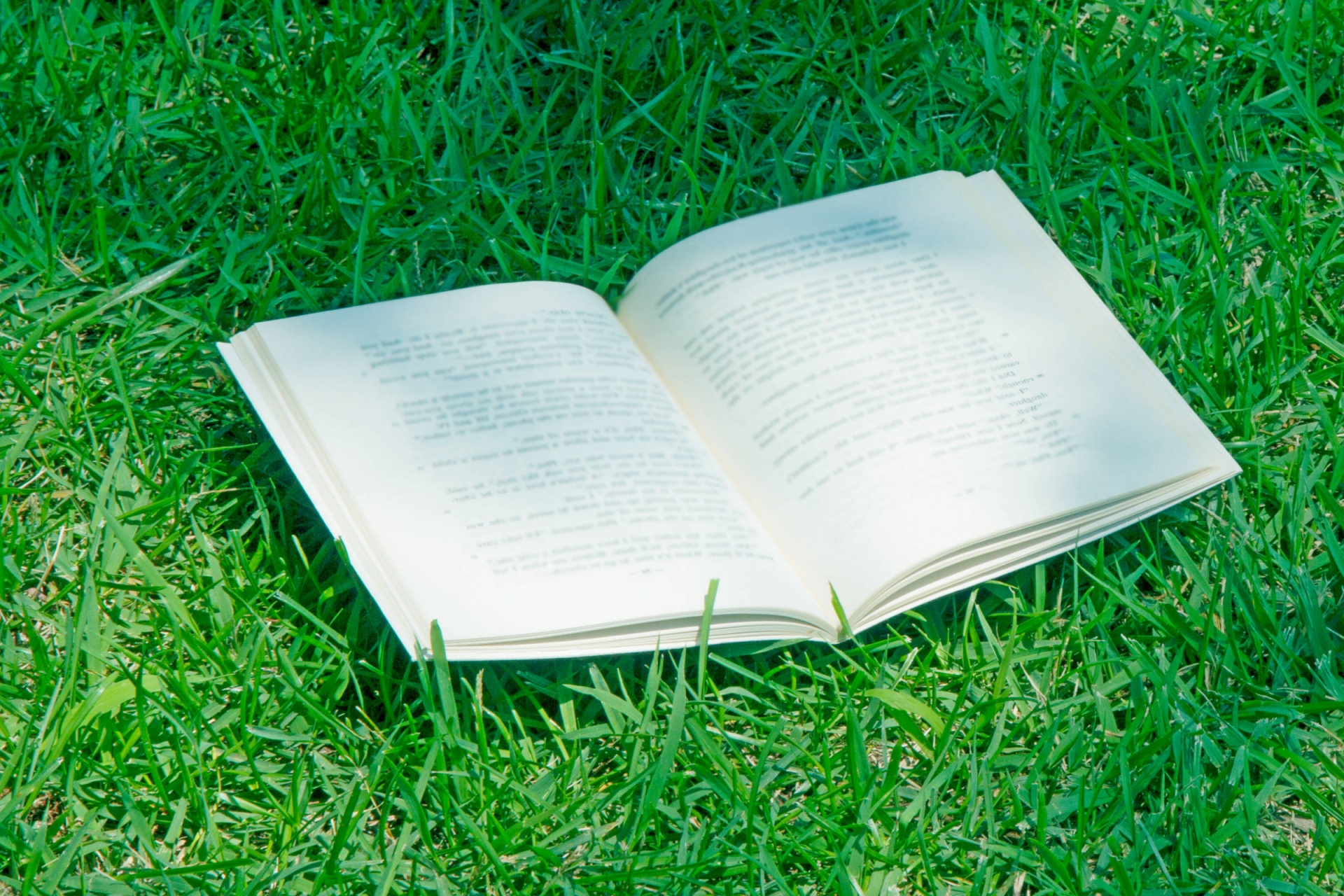
入学準備
【文学部】履修の組み方|京都大学の学部・学科別
解説記事

新入生の皆さん、合格おめでとうございます!
色々な準備を進める中で、「京大の履修の組み方が分からない……」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
詳しくは4月の学部ガイダンスで説明されますが、まずはざっくりと全体像を掴んでおきましょう。
基本的に吉田キャンパスと吉田南キャンパスを移動することになります。北部キャンパスには基本的に用がないので、京大より南に家を構えるとアルバイトや遊びの帰りに便利です!
学年ごとの必要単位がないため、単位は取れていなくても4回生には上がれます。ただし、その後は4回生を何回も繰り返す方式となるため、気づいた時には手遅れ、といったこともあります。
クラスでの繋がりが強いとも言われ、旅行に行ってるクラスもあるみたいです。
授業は「全学共通科目(般教)」と「専門科目」の2つの大きなカテゴリに分かれます。1回生のうちは全学共通科目が大半ですが、学年が上がるにつれて専門科目の割合が増えていきます。
卒業に必要な単位は全学共通科目で56単位、専門科目で80単位です。
56単位の中には以下のような細かい規定があります。
| 人文・社会科学科目群(人社) | 16単位以上 |
| 自然/統合科学科目群 | 6単位以上 |
| 外国語科目群 | 24単位以上 |
| 情報学科目群 | 6単位まで |
| 健康・スポーツ科目群 | 6単位まで |
| キャリア形成科目群 | 4単位まで |
| 少人数教育科目群 | 2単位まで |
人社は“文系”科目、自然群は“理系”科目のようなイメージでOKです。しっかり抽選科目を当てて楽単で固めましょう。ここは他学部の友達とも協力して1回生のうちに取り切りたいです。
なおILASセミナーについてはモチベーション高く取り組めそうであれば受けましょう。時間の余裕が欲しい場合は受講しないという方向もアリかと思います。
以下、外国語関連について少し解説します。
英語リーディング、ライティングそれぞれ4単位ずつ、合計8単位を取る必要があります。1回生のうちに取り切るのが理想です。
中国語、ドイツ語、スペイン語など8言語から選択します。初級・中級それぞれ8単位、合計16単位を取る必要があります。カリキュラム上は初級8単位を1回生、中級を2回生で取り終えます。初級4単位を取らないと中級科目を履修できません。
筆者の印象としては中国語が半分、残りの半分をスペイン語、ドイツ語で分け合うといったイメージで、その他はマイナー言語となり独力で勉強しないといけない場合があります。
筆者の履修経験から中国語について簡単に説明すると、初級は教科書に沿って授業が行われるものの、解説がなく難しい印象でした。授業を聴けばわかるはずですが、なかなか聴きとれるものでもありません。中級は各先生に授業が任されており、初級より簡単な教科書を使う先生も多いです。初級と違って先生を選択できるので、楽だと言われている先生を履修すると初級よりはるかに簡単に単位が取れるイメージです。
E科目は全編英語で行われる授業です。E1は日本人、E2は外国の先生が授業を担当します。E科目合計で8単位、うち外国文献購読(法・英)で4単位の取得が必要です。
全編英語のため、何を言っているかわからないことも多く、楽単を当てるまで待ちましょう。英語で発表する際に留学生が流暢な英語で質問してくることなどもあります。
なお外国文献購読(法・英)は「法」の文字があるものの、全学共通科目の扱いになります。内容は法律や政治の内容を外国の文献を読みながら理解するもので、学びたい科目や楽単度によって先生を選択して履修します。
卒業には80単位必要です。以下、科目別に解説します。
少人数のゼミである演習科目を4単位含む必要があります。
なお諸事情で演習科目が取れない場合、演習2単位あたり他の科目4単位を取得することで代替可能です。たとえば演習0単位の場合は76+8=84単位、演習科目2単位の場合は78+2=82単位が必要となります。コスパ的に演習科目4単位を履修するのがおすすめです。
実務関連科目は、様々な企業や団体の実務家の方々を非常勤講師として行われる講義です。2・3・4回生配当ですが、基本的に専門科目の中では楽単といわれています。
10単位までしか卒業要件に入らないので効率的に取っておきたいところです。
基礎法学および政治学から6単位以上履修する必要がありますが、基本的に履修を組んでいれば意識せずとも履修要件は満たすことになるでしょう。
筆者は政治科目の方が教科書の分量が落ち着いていてイメージがしやすいので、政治科目を多めに取っていました。ここは人の好みになると思います。
外国文献研究(英)は6単位を上限に専門単位に参入されます。
上述の「外国文献購読」とは異なるので要注意です!外国文献購読は必修単位である一方、こちらの外国文献研究は選択科目となります。なお、実はあまり知られていない楽単かもしれません。
1回生配当の入門科目が一番の楽単で、かつ1回生でしか取れないのでここはきちんと取っておきたいところです。1回生だからサボって良いと言うことはなくここである程度の余裕を持っておくと後々楽になります。
その後、2回生以降は半期あたり専門科目を14~18単位ほど取れていれば順調といえるでしょう。
なお、京大法学部は30%以上が留年するとされる、鬼門の学部です。文系学部の双璧をなす経済学部とは雲泥の差かもしれません。他の学部が試験終了してからも1週間以上は試験期間です。試験1ヶ月前だけ受験生に戻りましょう。
不安な人は自主ゼミに入ってみると良いかもしれません。法学部は勉強会が活発で、“さつき会”や“げんぽー”“こくせー”など、興味のある分野に合わせて多様なゼミがあります。
法学部は出席点がなく、ネットにレジュメがアップされる場合も多いです。自力で出来る人は授業に出席せず自分のペースで勉強を進められるため、計画性のある人はアルバイトに就活、起業やサークルなど色々なことに力を入れられるともいえます。
コスパ良く単位をとりたい方は、大学院進学から法曹を目指す通称「ガチロー勢」を味方につけ、ノートや授業メモをいただきましょう!
法学部は他の文系学部とは比にならないほどしんどい学部でしょう。ただし、しんどいのは試験前1ヶ月で、他は自由に遊びやバイトができる学部とも言えます。一抹の不安を抱えながらも、専門の授業にも出席せず焦って勉強をしていた筆者でもなんとか卒業できそうです。
日々の実験や桂流しのある理系学部も大変です。自分たちだけではないと思って頑張りましょう!
LINE登録はお済みですか?
京大mapの記事をお読みいただきありがとうございました。