
入学準備
スポ身ってどんな授業?東大生が解説してみた【東大授業用語②】
解説記事
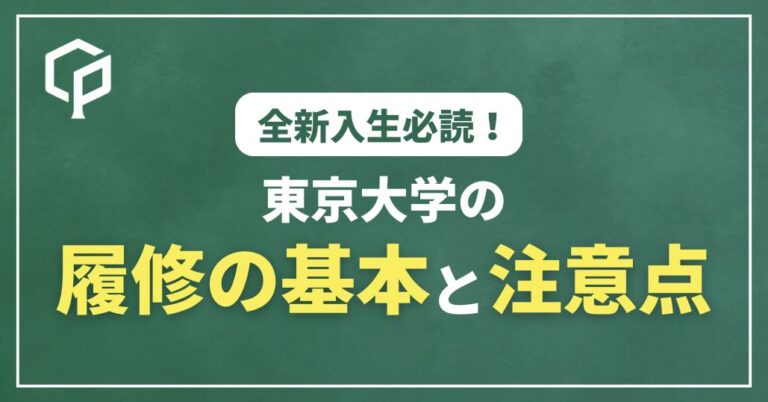
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます🌸
「早速どんな授業をとるか考えたいけど、東大の履修の組み方がよくわからない……」という方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、UTmap編集部が皆さんに、履修の組み方の基本と気を付けておきたい点について解説します!
なお、各科類のより具体的な履修の組み方についてはこちらの記事も参照してください。
大学では高校時代とは異なり、時間割を自分で決めることができます。言い換えれば、「どの授業を取り、どの授業を取らないか」を自ら決める必要があります。この選択のことを「履修」と言うのです。
履修を行うにあたっては、ある程度の制限が設けられています。逆に言うと、その制限さえ押さえていれば、あとは基本的に自由に授業を選択することもできるのです。自分に合った時間割を作れるようにポイントをしっかりと押さえましょう。
履修を決めるときは基本的にUTASのシラバスを用います。その中で気になる授業を見つけた場合、とりあえずお気に入り登録をすれば、ITCーLMSで時間割が表示されたり教授からの情報を得たりできます。どんどんお気に入り登録していきましょう。
履修を考える上でまず行うことは「必修科目」を埋めることです。東京大学における必修科目とは「基礎科目」のことで、選択の余地がなく必ず受けることになります。基礎科目の時間割や教授の情報などは、UTASのシラバスや教養学部の科目紹介から自分の科類とクラスを探すことで確認できます。自分のクラスの必修科目が見つかったらどんどん時間割に書き込んでいきましょう。
また、総合科目のL系列だけは必修科目のような扱いであるためここで紹介します。一年生は総合科目L系列の英語中級(または上級)の教授を選ぶことになります。「クラス別 or 全学」という選択肢はあるものの、一般的に一年生の多くはクラス別から授業を選ぶ傾向があります。
なお、初年次ゼミナールの選択もありますが、これは合格・不合格のみで評価され、成績に関わらないため興味を持った授業を選択すれば問題ありません。
履修において選択の余地があるとしたらこの「総合科目」と「主題科目」のみです。一方、これらを1年生のSセメスター(1S)で取る必要はなく、時間のある2Sなどにまわす人もたくさんいます。成績の観点でも1Sでは必修科目に集中する方が得策なので、無理にキャップ制(後述)ギリギリまで履修する必要は全くありません。
総合科目ではたとえば「AからDの2系列以上にわたり6」などと書かれています。この場合は「A系列:4単位、C系列:2単位」「A系列:2単位、B系列:2単位、D系列:2単位」などの取り方で問題ありません。面白いと思った授業を履修してみましょう。
なお主題科目は2単位取れば良いので、4つの分類のうちどれか1つを選びましょう。
4月の末までに履修登録期間の締め切りがあり、5月10日頃までに履修確認・修正期間があります。この履修登録期間、遅くとも履修登録修正期間までにその授業を受けるかどうかの判断をすることが一般的です。つまり何回か授業を受けてから履修するかどうかを決められます。いわゆる「もぐり」をするかどうかの判断もこの期間ですることが多くなっています。
ここでは履修において知っておくべき内容を紹介します。
『履修の手引き』には「進学選択が可能となる条件」と「前期課程修了要件」という2種類の必要単位数がありますが、基本的には2Sまでに「前期課程修了要件」の単位数を取ることを目標として履修を組むと良いでしょう。
基礎科目は全て必修科目であるため選択の余地がありません。気をつけるべきは総合科目で、きちんと複数の系列にまたがって単位が取れるように授業を選ぶ必要があります。
「キャップ制」とは履修できる単位数の上限がセメスターあたり30単位以下と決められている制度のことです。このため、1Sでは基本的に週15コマというのが基準となります。必修科目だけで11〜12コマ程度は埋まるため、意外とその他の選択肢が狭いことが分かります。
効率を求める人の中には、たとえば1日の1限から5限まで授業を詰め込んで、なるべく空きコマを作らないようにする人もいるかもしれません。それができるならいいのですが、実際に授業を受けてみるとかなりきついと感じるのではないでしょうか。
個人的には1日あたり多くても4コマ程度が良いと思います。また、空きコマがあるとその時間を授業の復習や予習、睡眠の時間などに使えるため意外とありがたく感じるでしょう。キャパオーバーしない程度の時間割作成をおすすめします。
東大の成績は100点満点で評価され、5段階の評価基準があります。
また、「優3割規定」という制度が存在し、優以上をとる生徒は大体3割までに制限されています。こうした制限の中、点数を取るために重要なのは授業の先生の選び方です。特に『逆評定』という冊子を読むことで、その先生がどんな人で、テストやレポートの難易度がどのくらいかをある程度知ることができます。
それ以外にも先輩からの話などでも先生の人柄や授業の進め方などを知ることができるので、色々なところから情報を集めてみると良いでしょう。
選択授業で何をとるか迷っている場合は、情報が集まりやすい授業をとる方が良いでしょう。たとえば先輩が受けていた授業や、友人や知り合いが受けている授業を取る方が、過去問や試験対策プリント(通称シケプリ)を入手できる確率が上がったり、授業のよくわからない箇所を友人に相談したりすることができます。
実は「進振り」までの成績の中で大部分を占めるのは必修科目です。必修科目で注意すべきは、一度単位を取ると点数が変えられない上、単位を取れなかった際の再履修では満点が75点になっている点であり、一度目の履修できちんと点数を取っておく必要があります。
そのため、成績のことを考えると特に1Sの間は総合科目や主題科目より必修科目に集中する方が良いかもしれません。興味がある授業を我慢する必要はありませんが、単位のために無理に総合科目などを取る必要はないことも覚えておいてください。
ここでは履修に関して調べていると頻繁に目にする用語の解説をします。
「セメスター」とは小学校などでいう「1学期、2学期」のようなもので、東大にはS(Spring)セメスターとA(Autumn)セメスターが存在します。
「ターム」とは各セメスターを前半と後半に分けたもので、Sセメスターの前半(4月〜5月)をS1ターム、後半(6月〜7月)をS2タームと表します。
また、Aセメスターの後の春休みをW(Winter)セメスターと表現します。
「追い出し」とは総合科目において必要単位数以上の単位を取ることで、成績の低い科目の重率を0.1にする戦略のことを言います。
重率の考え方は別途解説しますが、簡単に言えば科目ごとの重要度を示す指数です。必要単位に含まれる科目の重率は1、それ以上に取得した科目は0.1となります。そのため、多めに単位を取得することで、点数の高い科目を必要単位(重率1)に換算することが可能になるのです。
ただし、追い出しの作業は基本的に2Sの履修の時点で考えることであり、1年生の間はあまり考えなくても良いかもしれません。
ほとんどの人には関係のない話ですが、キャップ制を解放することができます。解放すると1Aと2Sにおいて、30単位以上の履修が可能になります。
解放条件は以下の通りです。
「撤退」とは主に基礎科目と総合科目において、単位を取ってしまうと成績の上書きができなくなってしまうため、あえてテストを受けずに欠席することで単位を落とし、次のセメスターで再度履修して良い点数を目指す戦略のことを言います。
もちろん、ただ単位を落とすだけの場合もあるでしょう。また、撤退をして再度履修しない場合、成績における撤退のメリットはないため、それならそもそも履修しないという選択をおすすめします。
進学選択が可能となる条件の単位数を満たしていなかったり、第三段階までの進学希望登録で内定がもらえなかったりした場合、2Sから1Aに戻ることになります。
この場合、取り損ねた単位の回収や志望学科へ内定するための成績向上を1年間かけて行うことになります。
大学の履修は、高校までとは大きく異なり、「自分で考えて選ぶ」ことが求められます。必修科目をきちんと押さえること、必要単位数やキャップ制を理解すること、無理のない時間割を組むことなど、最初に知っているかどうかでその後の大学生活や成績に大きな差が生まれます。本記事で紹介した基本的な考え方や注意点を押さえておけば、履修で大きくつまずくことは避けられるはずです!
ただし、実際の履修の組み方は科類ごとに異なる点も多く、おすすめの授業や注意すべきポイントも変わってきます。
こちらの記事では、科類別により具体的な履修の組み方や時間割の考え方を詳しく解説していますので、ぜひ自分の科類の記事もあわせて確認してみてください。
履修は、大学生活のスタートを左右する大切な一歩です。納得のいく時間割を組んで、充実した東大生活をスタートさせましょう!
LINE登録はお済みですか?
UTmapの記事をお読みいただきありがとうございました。