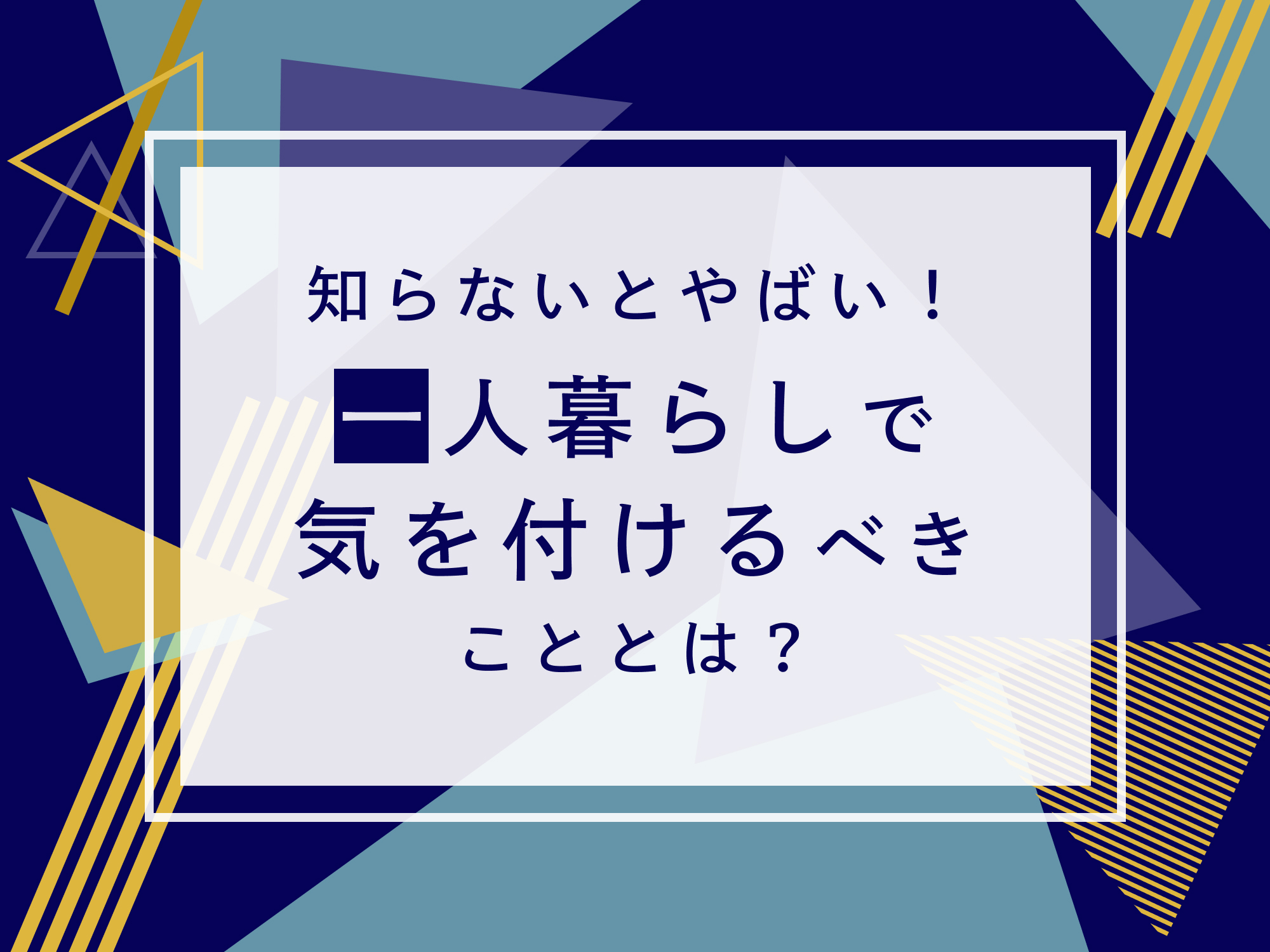
入学準備
知らないとやばい!一人暮らしで気を付けるべきこととは?
解説記事

新入生の皆様、東京大学へのご入学おめでとうございます! 春から新生活、希望に胸を膨らませて赤くない駒場の門をくぐる方も多いことでしょう。
しかし、当然遊び惚けている場合ではありません。ご存知の通り東大には2年生時に、3年生以降の進学先を決められる進学選択という制度があります。もちろん、2年生までの前期課程において、専門分野に縛られることなく、さまざまな学問を興味の赴くままにつまみ食いできるのは進学選択という制度の最大の魅力と言えます。その一方、複雑な進学選択の仕組みが理解できていなかったり、サークルやアルバイトに力を入れ過ぎたりしたせいで希望の学部に進めない…などという悲劇も枚挙にいとまがありません。
この記事では、読者の皆様が、進学したい学部に進学できるよう、そうでなかったとしても、納得して3年生の春を迎えられるよう、進学選択とは何か、どこに落とし穴があるかを解説していきます。
東大の学部生活は基本的に、2年間ずつの前期課程と後期課程に分かれます。文科Ⅰ類、理科Ⅱ類といったような科類に分かれてこそいるものの、前期課程の2年間は皆教養学部に所属しているのです。そこから後期課程、いわゆる「専門」に進む際の学部・学科による選抜プロセスが進学選択と呼ばれるものです。
当然、それぞれの学科には定員が設定されています。進学希望者がその定員を上回ったとき、前期課程での成績で進学できるか否かが決定するため、駒場生にとって成績は非常に大きな意味を持ちます。
前期課程は、2年生への進級はフリーパスです。どれだけ成績が悪かろうが、単位を取っていなかろうが、2年生になれないことはありません。しかし、2年の前期、すなわちSセメスターからAセメスターの進級には、一定の要件を満たす必要があります。各科類毎に定められている「進学選択が可能となる条件」(詳細は履修の手引きを参照ください。)を満たさなければ、そもそも進学選択に参加することすらできず、「降年」という形で再度1年生のAセメスターからやり直すこととなります。
進学選択に参加したとしても、学部への内定がもらえていない場合や、そもそも進学選択に参加しなかった場合にも、やはり降年という形で1年生に戻ります。ただ、本稿では詳細は省きますが、進学選択の際に参照される成績は平均点を基本とするため、あえて降年し、1年使って平均点を高めてから進学選択に参加する戦略も存在します。
2年生のSセメスター末は「進級の審査」と「進学選択」が同時に行われる大事な時期です。誤解しがちなのは、「進学選択に必要な単位数さえ確保すればよい」と考えてしまうことです。実際には、それだけでは大きなリスクがあります。
進学選択で参照される成績は「平均点」が基本となり、この平均点は文系なら56単位、理系なら63単位の前期課程修了要件をもとに計算されます。したがって、必修科目を後回しにして履修しないまま2年Sセメスター末の進学選択を迎えると、その科目は「0点」として扱われ、平均点を大きく下げてしまいます。
さらに、もし前期課程を修了しないまま進学選択を通過した場合でも、2年生のAセメスターは「持ち出し科目」で埋め尽くされることになります。これは、前期課程に在籍しながら後期課程の授業を先取りする形になるもので、カリキュラム上必修であるため避けられません。2年生のAセメスターになって駒場と本郷を反復横跳びしなければならない事態を避けるためにも、計画的な履修・単位取得が必要なのです。
理転・文転が出来るのは東大のカリキュラムの中でも大きな魅力の一つと言えるかもしれません。しかし、特に文科生が理系学部への進学を希望する、理転の場合には大きな障壁があります。それが要求科目です。
Aセメスターでしか履修できない科目を履修していることが、文科生が理系学科に進学するための条件となっています。上述の通り、進学選択の際に参照されるのは2年生のSセメスター末の成績。つまり、1年生のAセメスターが始まった段階で理転を視野に入れて履修計画を組んでいなければストレートに理系学部に進学するのは不可能ということになってしまいます。
文転の場合には、要求科目は存在しないものの、理転・文転ともに要望科目と呼ばれる、学科が進学を希望する学生に履修を推奨している科目も存在します。これは要求科目と違い、進学の条件ではないものの、人気学科への進学を希望する場合は履修を考慮すべきでしょう。履修計画の相棒、履修の手引きをよく確認することが必要です。
文科Ⅰ類から法学部など、科類と学部・学科の組み合わせによっては定員割れを起こしており、進学選択のために高い成績を取る必要はないと高をくくっている人もいるかもしれません。しかし、決してそんなことはありません。
大学卒業後の進路によっては前期課程を含めた学部時代の成績が重要となる場合があります。弁護士など、特殊な業界での就職活動や、大学院の入学試験は学部成績が重視されかねません。そのような観点からも、進学選択には大きな影響を与えないとしても、長期的な視野をもって履修計画を立てるのが最善であると言えます。
与えられた時間割をこなす高校までと違い、自分で計画を立て、履修する授業を決定しなければならない大学生活。冒頭では遊び惚けている場合ではない、などと書きましたが、勉強に精を出すのも、サークルやアルバイトに励むのも、もちろん遊び惚けるのも自由です。ただ、考えなしに易きに流れてしまうその前に、今自分の前にどれだけの可能性が広がっているのか、自分が本当にやりたいことは何なのか、そのために何をすべきなのか、一度立ち止まって考えてみてもいいかもしれません。
LINE登録はお済みですか?
UTmapの記事をお読みいただきありがとうございました。