
プログラム
【松尾研】AI経営寄付講座2026が開講します!
解説記事

体験活動プログラムとは、東京大学が長期休みを中心におこなっている体験活動型のプログラムです。国内ボランティアや国際交流など、活動内容は多岐にわたります。
今回は、そのなかでも、東日本大震災・原子力災害により甚大な被害を受けた福島県浜通り地域 にてフィールドワークを行うプログラム「帰還困難区域の『 街づくり』を考える。ー『復興』の現場に生きる人々の想いとともに ー」から、藤澤様と根本様に取材させていただきました。
UTmap編集部:
このプログラムおよび、お二方について伺ってもよろしいでしょうか。
藤澤:
公共政策大学院修士 2年の藤澤と申します。今年度のプログラムの主催をしております。昨年度は参加者としてこちらのプログラムに参加していました。
もともと私は国際問題に関心があり、これまで福島や復興、まちづくりといったテーマに直接関わったことはありませんでした。ただ、ずっと心のどこかで、東日本大震災や原発事故、その被害を受けた地域の今をきちんと知りたいという思いがありました。
そんな中で、昨年、体験活動プログラムを探していた時に目に留まったのが、2024年度のこのプログラムのサブタイトル「復興に対する多様な『想い』に触れながら」という言葉でした。当事者の方々の多様な視点に触れながら学べる点に強く惹かれ、参加を決めました。
根本:
工学部都市工学科4年の根本と申します。2023年度にこのプログラムに参加し、2024年度にはプログラムの主催をしていました。もともと災害・復興には興味があり、指導教員である開沼博先生(東京大学大学院情報学環)が前期教養課程で担当されている「現代社会論」という講義でこのプログラムの存在を知りました。
ニュースなどでは避難指示や処理水といった大きな話題を目にすることが多いですが、この地域の現状は実際どういうものなのか、自分の目で見てみたかったというのも理由の一つです。
藤澤:
このプログラムは、原発事故によって長期的な避難が強いられ、現在も町内に帰還困難区域が残っている福島県の双葉町・浪江町・大熊町・富岡町を訪ねて、現地の人々と対話しながらこの地域の復興まちづくりを考えていくものになります。
UTmap編集部:
現地で調査を行うということですが、具体的な内容について教えてください。
藤澤:
まず参加者は「医療」や「教育」、「産業」といったテーマごとにチームに分かれます。それぞれのチームが、関心のあるテーマに対して自分たちで問いを立て、現地の現状や取り組みについて事前調査を進めながら、ヒアリングに向けた準備をします。
そして現地では、自治体職員の方や地域の事業者、住民の方々などにヒアリングを行い、その後、得られた声や情報をもとにチーム内で議論を深め、自分たちなりの理解や視点を整理していきます。最終的には、その成果を現地の方々に向けて発表する場を設けており、地域の方々と意見交換を行います。
UTmap編集部:
このプログラムの背景について教えてください。
根本:
まずは昨年度、私が主催者だった年のプログラムについてお話しします。私のさらに前の年(2023年度)の主催者の方といろいろ話をしながらプログラムを設計していったのですが、その方から引き継いだ重要な問題意識として「地域に関わるってどういうことだろう」というものがありました。
体験活動プログラムやフィールドスタディ型政策協働プログラムなど、大学生が普段接点のない地域を訪れる機会は多数用意されています。しかし、地域に3回ぐらい入り、それだけで「分かった」ことにしてしまうのは暴力的なのではないかということです。大学生がある地域を数回訪問して、「この地域はこうあるべきだ」と提案して帰っていくのは望ましい地域との関わり方なのか、そこを捉え直したいと考えていました。
では提案ではないのなら何ができるのか。まずは真摯に謙虚に地域に入って、人々の声を聞く中で勉強することなのだと思います。そのうえで、地域の方も気づいていなかったようなことを何か掘り起こせたらいいなと。
さまざまな東大生が考えるべきことの多いこの地域に来て、思考を巡らせ、何か新しいものをもたらしながら勉強するというのが、このプログラムの大きな目的になるのかなと思います。
藤澤:
そして、今年度のプログラムの背景ですが、「復興」をとらえなおすことが一番の問題意識としてあります。2025年度のテーマを考える上で色々な記事に目を通していたのですが、そのなかで特に印象に残ったのが、飯舘村の村長のインタビュー記事でした。そこには、行政が主体となって復興を進める中で、住民にとって「復興」という言葉が遠のいているのではないか、そんな思いが書いてあり、昨年私自身が参加した時に感じたものと重なる部分がありました。
国や行政の政策など外から与えられる復興だけではなく、地域の人々が主体的に思いをのせて取り組むことで、福島が前に進んでいると強く感じたんです。「復興」という言葉ひとつをとっても、主体的な動きのあるものがすごく大事であるという問題意識を、地域の実態と合わせて深めていきたいなというのが出発点としてありました。
そこで、復興の現場で起きている地域の実践や、そのなかでの課題を丁寧に理解して解きほぐしたいという思いから、今回のテーマ「『復興』の現場に生きる人々の想いとともに」に至りました。
UTmap編集部:
藤澤さんや学生の強い思いが反映されている今回のプログラムですが、ほかの体験活動プログラムとは異なる魅力を教えてください。
藤澤:
このプログラムは、学生が主体であることが特徴的です。昨年初めて参加したときは、プログラムの設計や準備、現地での進行などは大学の職員の方が主導するものだと思っていました。ですが実際には、その大部分を運営メンバーの学生ひとりひとりが担っていたので、とても驚きました。自分ごととしてこの地域を考える学生が運営スタッフのなかにたくさんいたことが刺激的でした。
また、社会人になってからも駆けつけてくれる先輩もいて、単発ではない地域に根付いたプログラムにしていくという思いが、言葉だけではなく現れていることに魅力を感じました。今年もそのようなプログラムを作っていけたらな、と考えています。
根本:
私も学生主体であることは大きな魅力だと思います。体験活動プログラムの事務局の方からも、「学生が主催でやってくれるところはあまりないし、そこに価値を感じている」と以前お話いただいたことがあります。
藤澤さんのおっしゃる通り、基本的にこういうプログラムは、行政や大学が主導するものが多いと思うのですが、このプログラムは学生が主催です。例えば、プログラムの設計からアポイントメントまで、ほぼすべてを学生が担当します。みんなで共に作り上げていくという感覚を得られることはすごく良いところかなと思っています。
UTmap編集部:
学生が運営の主体とのことですが、どのような人が運営スタッフとなっていますか。
根本:
運営と参加者というふうにはっきりと分けていませんが、このプログラムに参加して2年目の学生や大学院生などに、運営のスタッフを担当いただいています。
UTmap編集部:
具体的に、このプログラムでしかできない体験などはありますでしょうか。
根本:
自分の裁量に応じて地域に入り込むことができることです。私はこのプログラムに参加した際、地域の飲食店事業者の方々にお話を聞いて回るということをしました。プログラム後も1年半以上それを続けていまして、現在は研究の形でアウトプットをしています。プログラムを超えてさらに地域と関わり続ける余地があるのもこのプログラムの特徴的なところだと考えています。
藤澤:
これまでの自治体の方との繋がりもあるので、たくさんの方がヒアリングに協力してくださります。今年から参加する方も、その多様なネットワークに飛び込んで、いろんな人から直接顔を合わせて話を聞くことができます。
私は、去年このプログラムで初めて福島を訪れましたが、そんな状況でも温かく迎え入れて色んなことを教えてくださる環境があるのはとても貴重なことだと思いました。

UTmap編集部:
このプログラムでは、成果を学会発表するとお聞きしました。どのような発表をしているのか教えてください。
根本:
新規性・独自性といった面で、学会発表ができるクオリティの調査をすることを目指しています。実際に昨年度は、すべての班が11月に学会発表をしています。
私自身、このプログラムの別の参加者の方と、「福島復興を再考する:双葉町・大熊町・富岡町・浪江町の飲食店事業者の語りから」というテーマで継続して研究を行っています。
しかし、全員が学会発表しなければならないというわけではもちろんありません。学術的なこと以外で関わりたいという方を受け入れる土台も十分あるのかなと思っています。
藤澤:
学会発表が目標と聞くと、ハードルが高いように感じる方もいるかもしれません。私も最初は戸惑いました(苦笑)。ですが実際に昨年参加してみて、学会発表ができるくらいの新規性を見つけようとチームで努力したことで、より密度の濃い学びと経験につながったと感じています。
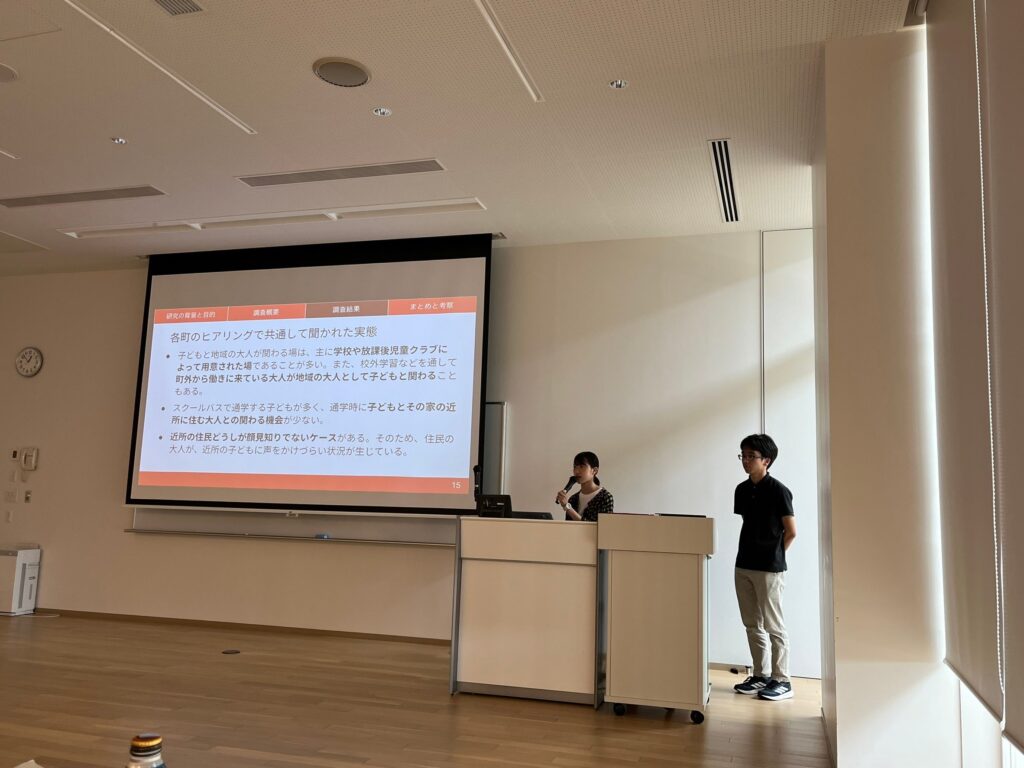
UTmap編集部:
プログラム終了後も、学会発表という形で福島に関わり続けている人が多いようですが、それ以外の形で福島と関わっている人はいますか。
根本:
例えば、プログラム対象の町の一つ、浪江町には「うけどん」というゆるキャラがいます。うけどんのファンクラブ会員になって、年数回自宅に届く会報を読み、うけどんグッズを使うという形で関わっている人もいます。私もそのうちの一人です。
藤澤:
私は、理想としては研究を継続することで地域に関わりたかったのですが、体力との兼ね合いでプログラムの運営側としてかかわることにしました。この企画を考えるなかで、またこの地域のことを考え続けられることが嬉しかったです。昨年度、プログラムに参加して得られた経験を次世代に引き継いでいけたらと考えています。
また、私以外の昨年度の参加者で、このプログラムをきっかけに福島に関連する授業をとったという話を聞きました。小さなことでも福島と関わっている人が増えていると感じています。
UTmap編集部:
今までのお話で、学生主体のこのプログラムの魅力がたくさん伝わってきましたが、どのような学生にこそこのプログラムに参加してほしいと考えていますか。
根本:
このプログラムは、文理や学年関係なく様々な視点を持ち寄って様々な議論をできることが魅力です。1〜2年生の方が参加してくださることが多く、3〜4年生や院生の方は忙しく、なかなか参加しづらいところがあるかもしれません。
しかし、他の専門の人と関わり合う機会はあまりないですし、同じテーマについて違う視点から議論をするのは良い経験になるなと実感しています。3〜4年生や院生の方にも積極的に参加していただきたいです。
藤澤:
社会や地域のリアルな課題について、自分ごととして自分の力で考えてみたいという思いを持った人に参加していただきたいです。手触り感のある学びは学部や院の研究だけではなかなか得られないので、そんな経験を積みたいという方にぜひ来て欲しいです。
また、これまで福島や復興といったテーマに触れてこなかった方にも、臆せず参加してほしいと思っています。
UTmap編集部:
それでは最後にこれを読んでいる皆さんにメッセージをお願いします。
根本:
このプログラムは、関わり度合いや学部・学年を問わず様々な学生を受け入れております。様々な学生がいるからこそ得られる価値とか魅力があると思うので、ぜひ多様な方にこのプログラムを見つけていただき、まずは参加を検討していただきたいです。
藤澤:
このプログラムではたくさんの出会いがあり、その出会いを通してきっとみなさんの可能性や世界が広がると信じています。夏休みにお会いできるのを、楽しみにしています!。
改めて体験活動プログラムは、東京大学の学部生と院生が参加可能な体験型教育プログラムです。今回記事で紹介したプログラムだけではなく、国際交流や、国内の社会貢献活動など様々な魅力的なプログラムが多数用意されています。こちらのWebサイトにて、体験活動プログラムが紹介されているので、ぜひご覧ください。
今年度の「帰還困難区域の『街づくり』を考える」の募集は、以下の通りです。
LINE登録はお済みですか?
UTmapの記事をお読みいただきありがとうございました。